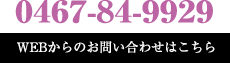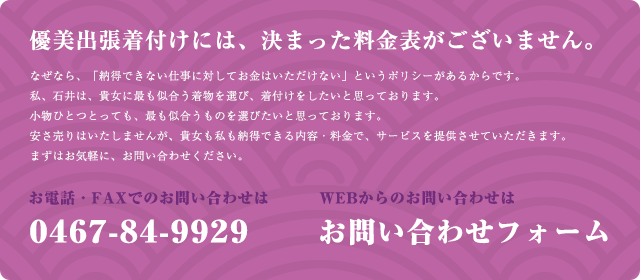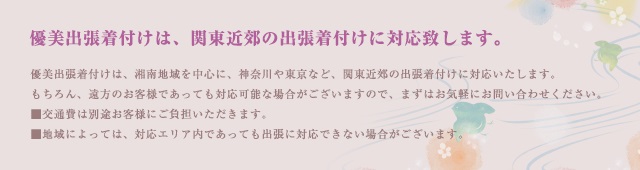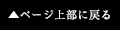2014年8月11日![]() きものを訪ねてその1、会津木綿
きものを訪ねてその1、会津木綿
旅行にいくと、必ず探すのがその土地で育まれた染織品で、時に家族の白い目に耐えつつ、郷土資料館などとセットで見てまわります。
今回は会津へ行きました。昨年度の大河ドラマ八重の桜では、会津木綿が、生活に中に欠かせないものとして、描かれていました。糸取り、糸ぞめ、機織、裁縫、女性にとって大切な仕事として。戊辰戦争後には、生活の糧を得るために織りあがった反物を売り歩くシーンも出てきます。
江戸時代の初期、伊予松山藩主である加藤嘉明が前領地から織氏を招いて技術を伝えてのが其の始まりとされています。その後、初代会津藩主保科正之が綿花の栽培を会津で奨励したことにより定着しました。ハタオリは農民だけでなく、藩士妻女の内職としても、行われ会津藩の保護政策のもとで、次第に発達しました。厚地で丈夫、肌合いがよく、保湿性、吸汗性にも優れた会津木綿は、寒暖差の激しい会津風土の中で人々の生活に欠かせないものとなりました。
化学染料と機械織が導入されてからも、安価で丈夫な会津木綿は大変重宝され、一時期、30件の織元があったようですが、今は2件を残すのみ。着物や小物のみならず、洋服や、文房具などにもアレンジされ、今に会津木綿の素朴な魅力を伝え続けています。
衣の暮らしと女性(歴春ふくしま文庫)によると、戦前までは、衣料品を自家製で賄うことはごく当たり前に行われていたそうです。糸をつむぎ、染色をし、織り・・・この布に仕上がるまでの大変な労苦があるために、一反の着物を全くあまらせること無く、大切に仕立てたのでしょう。繕いなおし、子供たちへ仕立て直し、半纏や、オムツや、雑巾など、完全に使い果たす。作った人々と同じように、素朴で力強い布は、跡形も無く消えていったのかもしれません。小さな布の切れ端を、縞帳に残して。最も、素朴な柄ともいえる縞は、限りある反物の幅、限りある色彩の中でも、千にも万にも変化していきます。たゆまなく、母から子へと引き継がれてきた技術や心があるからこそ、着物は美しいのかもしれません。それを私たちは享受している。ありがたいことだと思います。
参考資料 歴春ふくしま文庫 衣の暮らしと女性
「400年の伝統を持つ縞柄の伝統美」 (リーフレット)