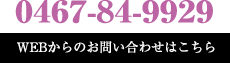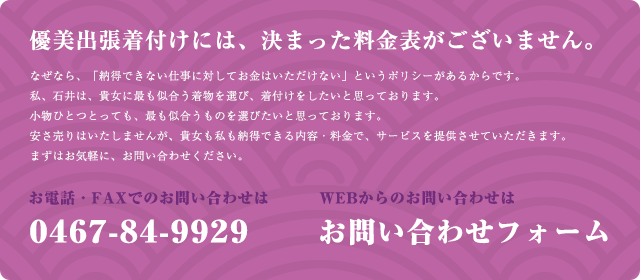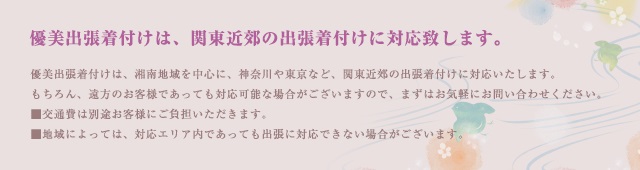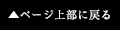2017年11月21日![]() 落語長屋の大家の独り言~霜月号
落語長屋の大家の独り言~霜月号
十七年霜月号
江戸の火事
江戸が火災都市と呼ばれるのは260年間に1798件の火災があったこと、大火は京都・大阪が各8回であったが江戸は28回も起こったことによる。
そして、江戸の火事の特色は冬から春先に集中していることであった。
北ないし北西の冷たい風が吹きつのり、数十日も雨が降らない乾燥状態になるからである。そこで毎年10月になると、きまって火の用心の町触れ出た。
安政元年(1854年)は、風の激しい日には拍子木が打ち鳴らされたら、湯屋、商店は直ちに店を締め町役人(家主ら)は火元を調べて回る。
蕎麦うどんなど火を使う商売は終える。料理屋、煮売り屋、酒屋は店先に出ている行燈や提灯を急いで取り込む。道端の屋台店も引き払う。家ごとに路に水をまき、水桶に水を入れおく。深夜には30分ごとに町内を見回れという町触れも出た。
お触れとして出された「火の元の掟」には①火の元をおろそかにしたものは町内を立ち退くこと②風の激しいときは公用のほかは外出しないこと、また屋根の上や家の外に水を打ち、桶などに水を汲んでおくこと等、また、長屋・店借りの者はもちろん、表店の者も加わり5人3人の組を作り、火の用心を心懸けること。等の掟が出された。江戸の町は片町もあったが、普通道路を挟んだ両側で構成されている。
道路には木戸があり、午後10時ころから翌朝6時ごろまで、治安のため閉鎖される。すぐわきの木戸番小屋には町から雇われている番人(番太郎)がいた。給料が少ないため焼き芋を売って生計を立てていた。また、向かい側にある自身番は町内の治安維持、消防、事務、寄合に利用される場所で、かっては地主自身が詰めていた。
その費用は番人の費用を含め、地主が負担する町入用という経費から支出された。
何町がが組合を作って共同経営している自身番もあった。大きな町のでは家主、店番、各2番人1の5人組が自身番の管理運営を行った。自身番には捕物の道具や消防用具があり、屋根上には半鐘をつるした火の見まであった。
落語には「二番煎じ」や「火事息子」がある。特に「二番煎じ」は笑いが取れるので寄席では多くかけられるが、「火事息子」は最近少ないようだ。